(昨日投稿したつもりでしたが、うまくできていないようでした^^;)
ここでは介助・介護の問題を解決するきちほーしのアイデアを原案レベルでお届けします。
介助・介護のド素人が考えた妄想レベルのアイデアなので、生温かく見守ってください^^。
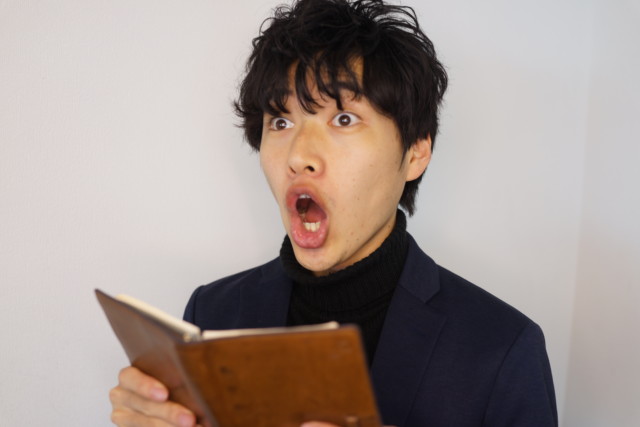
ひ、ひらめいた…!
アイスブレイク
(今週のお題「買ってよかった2022」)
アイスブレイクではきちほーしのことをよく知ってもらうため、はてなブログの「今週のお題」をヒントに、本題と少し外れたお話をします。
今週のお題は「買ってよかった2022」です。
きちほーしが買ってよかったのはBluetoothスピーカーですね。
 |
価格:1,490円 |
![]() 最近きちほーし家ではご飯時にテレビではなく、AbemaとかTVerとかをノートPCで見ています。
最近きちほーし家ではご飯時にテレビではなく、AbemaとかTVerとかをノートPCで見ています。
ご飯時じゃなくても一人で映画見たりする時もあります。
PCのスピーカーだと音が小さくて聞き取りづらいのでこのスピーカーを買いました。
有線のスピーカーもあるけど、PCにつけたり外したりを繰り返すと壊れる時があるんですよね。
だからきちほーしは極力無線を選ぶようにしています。
はじめに
一緒に考えてくれる人を見つけたい!
どーも!きちほーしです!
最近きちほーしは知的障害者の介助に関する本と高齢者の介護に関する本を読んで、介助・介護それぞれの問題点を勉強しています。
(きちほーしは介助・介護の意味をわかっていません^^;。
ここでは、知的障害者の場合は介助、高齢者の場合は介護と呼んでいます。)
本もまだ読んでいる途中で、現場を見たことすらないド素人です。
そんなド素人が介助・介護の問題を解決策を検討したいという思いで「こんなのあったらいいなぁ」というレベルの仕組みを考えてみました。
クオリティの低い原案レベルですが、あわよくば一緒に考えてくれる人を見つけたい!
そんなわけで現段階の浅~~~い知識で思いつくものをまとめてみました。
知的障害者の介助に関するアイデア
きちほーしの頭にはアイデアが2つあります。
1つは知的障害者の介助に関するアイデア、もう1つは高齢者の介護に関するアイデア。
ちなみに、高齢者の介護に関するアイデアは、そのまま知的障害者の介助に流用できると思います。
それは後日お話します。
介助の課題: ノウハウ集が作りにくい!
まずはきちほーしが本を読んで知った介助の課題についてお話します。
要介助者の希望と介助者の介助はズレやすい
介助の難しいところは、要介助者(介助を受ける知的障害者)の希望と、介助者が提供する介助の間にズレが生じやすいということです。
その原因は大きく3つあります。
- 要介助者がコミュニケーションが困難で、そもそも要介助者の希望がわからない
- 自分の収入を大きく超える買い物など、要介助者が適切でない希望を出してしまう
- 要介助者の意図を介助者が勘違いして、不適切な介助をしてしまう
これらのズレを解消するためにノウハウ集のようなものがあればいいのですが、実際は難しいのです。
- 【知的障害者向け訪問介助】介助の難しさ1 – 書籍「ズレてる支援!」4 - きちほーし知的障害者支援できるかな?
- 【知的障害者向け訪問介助】介助の難しさ2 – 書籍「ズレてる支援!」5 - きちほーし知的障害者支援できるかな?
障害者支援はたくさんの事例が必要
ノウハウは、発生した問題と、試みた対策と、その結果と、その他の要素を結びつけることによって作られます。
そして問題・対策・結果・その他の結びつきはすぐに見つけられるものではありません。
ある問題に対してこの対策で解決したつもりでも、実は思ってもいない要素が解決のポイントである場合もあるからです。
結びつきの精度を上げるにはできるだけたくさんの事例を集め、共通点を見つけ出すことが重要です。
特に障害者の場合は、コミュニケーションの問題で「その他」の要素が見えにくい分、共通点を見つけるにはたくさんの事例が必要だと思うのです。
解決策: 事例をみんなで共有し、ノウハウを皆で作ろう!
ノウハウの作成を容易にするためには、世界中の関係者が力を合わせればいいと思うのです。
「世界中」と大風呂敷を広げましたが、言葉や文化の壁もあるので「日本中」の関係者が力を合わせてもいいでしょう。
事例を日本中で共有し、問題の共通要因の抽出を日本中で行い、解決策の発案・解決策の評価も日本中で行う仕組みがあれば良いと思うのです。
以降、原案としてきちほーしが思い描く仕組みについてお話します。
概要: 自律分散型のノウハウ作成体制
きちほーしが思い描くのは、介助者および要介助者のプロフィールや日々の介助日誌などのデータをオンラインで収集し共有する仕組みです。
そしてオンライン上のスタッフがそれらのデータを分析し、Wikipediaのようにオンライン上にノウハウ集を作成します。
ちなみにプロフィールには、できること・できないこと、趣味嗜好、性格などを書きます。
さらに、各スタッフの活動に応じて報酬を分配します。
この仕組みはDAO(自律分散型組織)をベースにすることを想定しています。
スタッフの役割
ここでは、オンラインで参加するスタッフの役割についてお話します。

生データ入力者

日々の介助日誌や、要介助者および介助者のプロフィールなどの生データを投稿する人です。
介助日誌にはどんな問題があってどう解決したか、どんな気付きがあったか等を記入します。
プロフィールには、要介助者および介助者の得手・不得手、趣味嗜好、性格などを書きます。
例えば要介助者の得手・不得手については、下記のように書きます。
| 大項目 | 小項目 | OK/NG |
|---|---|---|
| 買い物 | 欲しい物を明示できる | OK |
| 支払額を理解できる | OK | |
| 使用できる金額を把握できる | NG | |
| どこで買えるか知っている | OK | |
| 掃除 | 掃除道具の場所を知っている | OK |
| 掃除道具の使い方を知っている | NG | |
| … | … |
要介助者の趣味嗜好は、例えば下記のような感じです。
| 大項目 | 小項目 | 趣味嗜好 |
|---|---|---|
| 料理 | 味付け | 調味料が嫌い |
| 食材 | 特定メーカーの食材しか食べない | |
| 掃除 | 清潔へのこだわり | きれい好き |
| … | … |
この生データ入力者は、介助者自身、あるいは介助者と要介助者のやりとりを眺めている第三者がやることを想定しています。
分析者

日誌やプロフィールなどの生データを使って、介助で発生した問題とその原因を分析する人です。
生データは世界中あるいは日本中から集められるので、似たような問題がある日誌を多数見つけられるはずです。
そしてそのような日誌がたくさんあればあるほど、共通点が見つかりやすくなると思うのです。
分析者は日誌とプロフィールを手がかりに、共通点を割り出し、分析結果を投稿します。
対策案作成者

分析者による分析結果を元に、問題の対策案を検討・投稿する人です。
対策案評価者

上記の対策案を実施し、効果的だったかそうでなかったかの評価を投稿する人です。
対策案の実施は介助の現場で行われるでしょうから、介助者自身がこの役割を担うケースが多いでしょう。
その他裏方の人たち

冒頭にも書きましたが、きちほーしはこの仕組みをDAO(自律分散型組織)をベースにすることを想定しています。
なので、各登場人物の活動に応じて報酬を配分する人や、この仕組みを運営・管理する人なども必要です。
おわりに
きちほーしの妄想にお付き合いいただきありがとうございました^^。
雑ではありますがこれがきちほーしが考えている、世界中の介助関係者がネットでノウハウを作れる仕組み、です。
もちろんこれは原案です。
この仕組みだけで問題が解決するとは思っていません。
プライバシーがあるので、生データをそのまま世界中で共有できないでしょう。
言葉や文化の壁があるので、世界中で共有するのはまだ先の話かもしれません。
分析者が日誌やプロフィールの字面だけ見てもデータとしては足らず、介助の様子を撮影した映像もあったほうがいいでしょう。
そうすると外出時にどうやって撮影するか、プライバシーをどうやって守るかの問題が出てくるでしょう。
この原案を元に、今後バージョンアップを進めていければと思います。
ではまた!