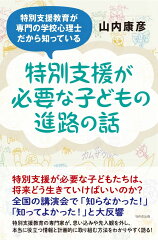障害ある子の進路は入学直前に取り組みがちですが、それでは後悔してもしきれないくらい手遅れな場合もあるのです。
入学の1年前どころか、もっともっともーーーーっと前から準備した方がいいのです。
この記事では、障害者の進路について解説した書籍「特別支援が必要な子どもの進路の話」についてギュギュギュッと要約してお話します。
これまでもグッと要約してお話してきましたが、さらにさらにギュギュギューーーッと要約しました。
今回と次回の2回に分けてお話します。
進路は親が調査し・親が考える
【障害ある子の将来設計】子どもの将来は学校にも行政にも任せられない現実を知ろう -書籍「特別支援が必要な子どもの進路の話」1
進路は「親が」高校卒業から逆算して決める
- 学校は療育・教育や短期的な進路には対応しても、長期的な進路は対応しない
- 高校卒業~就職・就労を見据えて親が考えておくことが大事
事前にしっかり調査しないと落とし穴に遭う
- 支援校に入学しようと思ったら入学条件の療育手帳がなく入学できなかった
- いずれ普通級に変わるつもりで支援級に入ったら授業が少なく普通級に戻れなくなった
障害者手帳を持つことのメリットとデメリット
【障害ある子の将来設計】「障害者」として生きるために必要な「障害者手帳」とは? -書籍「特別支援が必要な子どもの進路の話」2
障害者手帳は3種類
手帳の名前は自治体によって異なるが、概ね以下の通り。
| 手帳 | 対象者 |
|---|---|
| 身体障害者手帳 | 病気や身体の障害がある人 |
| 療育手帳 | 知的な遅れがある人 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | コミュニケーションや人づきあいに障害がある人 |
障害者手帳のメリット・デメリット
- メリット
- 運賃の軽減・税金控除・支援校の入学資格など
- デメリット
障害者の就労事情
【障害ある子の将来設計】卒業後なるべく就労できるようにするには? -書籍「特別支援が必要な子どもの進路の話」3
支援校高等部卒業者の進路
- 大半は福祉就労(月収5千円~数万円)
- 大半は生活介護
- 3割程度が一般就労(月収10万円~15万円)
- 6%程度の学校も
- コロナ期は1%程度にも
就職に不安を感じたら
- 17歳の時点で就労移行支援事業所の利用を検討しよう
- 離職が心配な時は就労定着支援の利用を考えよう
子どもの「社会性」に合わせて就労先を考えよう
- 17歳の時点での社会性に合わせて就労先を考えよう
| 社会性レベル | 可能な就労先 |
|---|---|
| 7歳(小1)(*) | 作業所 |
| 9歳(小3) | 就労継続支援B型 |
| 12歳(小6) | 就労継続支援A型 |
| 15歳(中3) | 一般就労 |
(*) 7歳(小1)レベルの社会性:「学校に行ける」「提出物を出せる」「係活動ができる」
社会性を検査する「S-M社会生活能力検査」
- 社会性レベルを検査できる
- 「身辺自立」「移動」「作業」「コミュニケーション」「集団参加」「自己統制」の6つの領域がある
高校進路 ~4つの高校進路と選び方のポイント~
【障害ある子の将来設計】高校は早いうちに選ばないと後悔する ~4つの高校進路と選び方のポイント~ -書籍「特別支援が必要な子どもの進路の話」4
4つの高校進路
| 大区分 | 小区分 | 障害者手帳 | 内申書 | 高卒資格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別支援学校 | 普通の特別支援学校 | 要 | 不要 | ナシ | 原則全員合格する |
| 〃 | 高等特別支援学校 | 要 | 不要 | ナシ | – 学力・作業・面接に関する試験で選抜 – 自力通学ができることも条件 – 「◯◯コース」のように支援校校内にあるケースも |
| 普通の高校 | 通常の高校 | 不要 | 必要 | アリ | ー |
| 〃 | 特別な高校 | 不要 | 学校による | アリ | 支援級から入学できたり、不登校でも卒業できたり、「特別」の内容は様々 |
進路選び7つのポイント
以下のポイントで事前にじっくり調査・検討することが大事
- 入学試験: 学力試験の有無・面接ほか
- 進級・卒業の条件: 期末試験の有無・卒業単位数
- どんな先生がいるのか
- 出席日数の必要量
- 少人数・個別対応の有無
- 卒業後の進路・就労の面倒を見てくれるか
- 学費
|
|
(参考)書籍概要
 |
価格:1,650円 |
![]()
タイトル
特別支援教育が専門の学校心理士だから知っている 特別支援が必要な子どもの進路の話
著者
山内 康彦
概要
特別な支援が必要な子どもたちは、どう生きていくべきか。小学校や中学校を卒業すれば、それで終わりではない。長い人生を自立して生きていくためには、進路について、なるべく早い段階から考えていく必要がある。
それには何が必要か。特別支援教育が専門の学校心理士である著者が、子どもたちの進路についての方策を具体的に説明する。
目次
第1章 18歳の出口から今の進路や療育を考える
第2章 中学校時代から高校までの進路を考える
第3章 小学校時代から中学校までの進路を考える
第4章 幼・保育園時代から小学までの進路を考える
第5章 未就学期に考えておくこと・取り組んでおくこと
第6章 子どもたちに学力と社会性を身につけさせる工夫(療育教材の紹介)