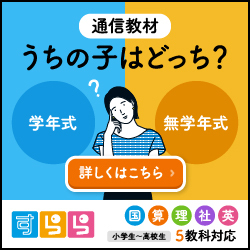この記事では、書籍「特別支援が必要な子どもの進路の話」で登場するIT療育教材について、きちほーしが要約・補足して紹介します。
ITが当たり前の時代に、子どもにもっとITを触れさせてあげたいと思う親御さんの参考になればと思います。
はじめに
どーも!きちほーしです!
きちほーしには知的障害を持つ子どものキチノがいます。
最近なんとか自宅で療育できないかと下にあるような療育に関する本を読んで勉強しています。
 | 誤学習・未学習を防ぐ!発達の気になる子の「できた!」が増えるトレーニング [ 橋本 美恵 ] 価格:1,650円 |
![]()
この本ではいくつかの療育教材が紹介されているのですがどれも手作り。
昔ながらのアナログ教材ですねー。
でも今はITが当たり前の時代。
子供の将来のためにももっとITに触れさせてあげたいと思うのが親心だと思います。
今回は、書籍「特別支援が必要な子どもの進路の話」で登場するIT療育教材について、きちほーしが要約・補足して紹介します。
 | 価格:1,650円 |
![]()
放課後デイで人気! 無学年式オンライン教材「すらら」
山内康彦さん著の「特別支援が必要な子どもの進路の話」でも紹介されているオンライン教材の「すらら」です。
放課後デイサービスにも導入されていて、とにかく利用した子どものウケがいいようです。
すららにはこんな特徴があります。
画像と音楽とストーリーで楽しく出題!
紙の本やプリントのような何十年と変わらないスタイルは、スマホやタブレット全盛の現代っ子には取り組む前から興味がもてません。
すららはパソコンやタブレットを使って、画像と音声で問題が出題されます。
さらにストーリー性をもたせて出題するので、楽しく学習が進められるのです。
できることから始めるプログラムで子どものモチベーションアップ!
通常学習と言えばその子の学年の学習を進めてしまい、その子がつまづているポイントに戻ることがなかなかできません。
その結果その子のできていないことが蓄積されて、できないことをやらされる勉強そのものを子どもが嫌がるようになります。
すららは、子どもがどんな課題につまづいていて、どんな課題ならできるのかを常に学習しています。
なので子どもにできている課題からスタートさせてモチベーションをあげつつ、つまづいている課題にうまく持っていくことができるんですね。
できる課題からスタートできる教材は子どもたちにとって魅力的です。
だから放課後デイサービスでもウケがいいのでしょうね。
その他
教材は未就学向けから高校三年生向けまであるようです。
定期的に「すららカップ」のようなイベントも行われていて、より意欲的にチャレンジする工夫も施されています。
障害の特徴がわかって訓練もできる! 「脳機能バランサー」
一言で「発達障害・知的障害」と言っても、どんな障害なのかは子どもにやってバラバラです。
子どもの障害の特徴がわからないと適切な療育もできません。
そんな時にはこの「脳機能バランサー」です。
定期的に発達年齢や発達指数が判定できる
通常は施設で知能検査を受けるのですが、予約がとれなかったり家族の理解が得られなかったりと様々な問題があります。
脳機能バランサーには発達年齢や発達指数を判定する機能があります。
知能検査は施設で年に一度しか行えませんが、この機能を使うことでより短い間隔で発達具合を知ることができます。
トレーニングゲームも充実
もぐらたたきやブロック、さめがめなど、13のゲームが用意されています。
これらによって「注意力」「言語力」「空間認識力」を楽しくトレーニングすることができます。
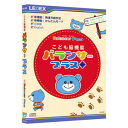 | 価格:5,000円 |
![]()
中学生以上には「高次脳機能バランサー」
脳機能バランサーは中学生までの子ども向けです。
中学生からは高次脳機能バランサーが提供されています。
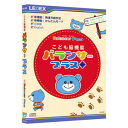 | 価格:5,000円 |
![]()
 | 価格:3,143円 |
![]()
VRでいろんな体験学習を! 「VRエモウ」
障害ある子は自分が体験しないと学ばない
障害ある子は一般的に「観察学習が苦手」と言われています。
観察学習というのは、例えば叱られている人を見て「あれをしたら叱られるみたいだな。自分はやらないようにしよう」みたいなのです。
逆に「あれをしたら褒められるんだな。自分も真似しよう」みたいなのです。
他人の体験を自分のことに置き換えて学ぶことを「観察学習」というようです。
障害ある子はこれが苦手なのです。
何度でも体験ができる
障害ある子は自分が体験しないとなかなか学習できません。
なのでより多くのことを体験させることが大事です。
そこで登場するのがVRエモウ。
このエモウは「放課後の話し合い」とか「面接」のようなシーン「コンビニの店員」などをバーチャルでトレーニングできるサービスです。
通常なかなかできない体験を、VRで何度も何度も体験できるのがすばらしいところです。
以前にもこの教材についてご紹介した記事がありますので、詳しくはそちらを見てみてください。
【自分語りできるかな?】VRって知的障害の療育にいいのでは?1
プログラムと障害ある子は相性抜群! 「すてむぼっくす」

障害ある子は例外やあいまいなことが苦手です。
じつはプログラムの世界も例外やあいまいなことが苦手なんですね。
「すてむぼっくす」は、STEAM教育と呼ばれるプログラミングや理数・工学分野の知識・教育方法を活用したレンタル教材です。
子どもたちの自立や成長を促す「プログラミング療育」を行うことができます^^。
様々なブロック教材やプログラミングアプリを使ってちょっとしたおもちゃを作るんですねー。
ものづくりの体験を通して、指先練習に加え、「順序立てて考える力」や「工夫する力」を育むことができます。
おわりに
いかがだったでしょうか?
今回は、書籍「特別支援が必要な子どもの進路の話」で登場するIT療育教材について、きちほーしが要約・補足して紹介しました。
- できることから始めるプログラムで子どものモチベーションを継続するオンライン教材「すらら」
- 何度でも発達年齢や障害の特徴がわかる「脳機能バランサー」
- VRで何度でもいろんな体験学習ができる「VRエモウ」
- 障害ある子の強みを伸ばす「すてむぼっくす」
これらに触れて療育とITスキルアップの両立を目指したいですね。
ではまた!